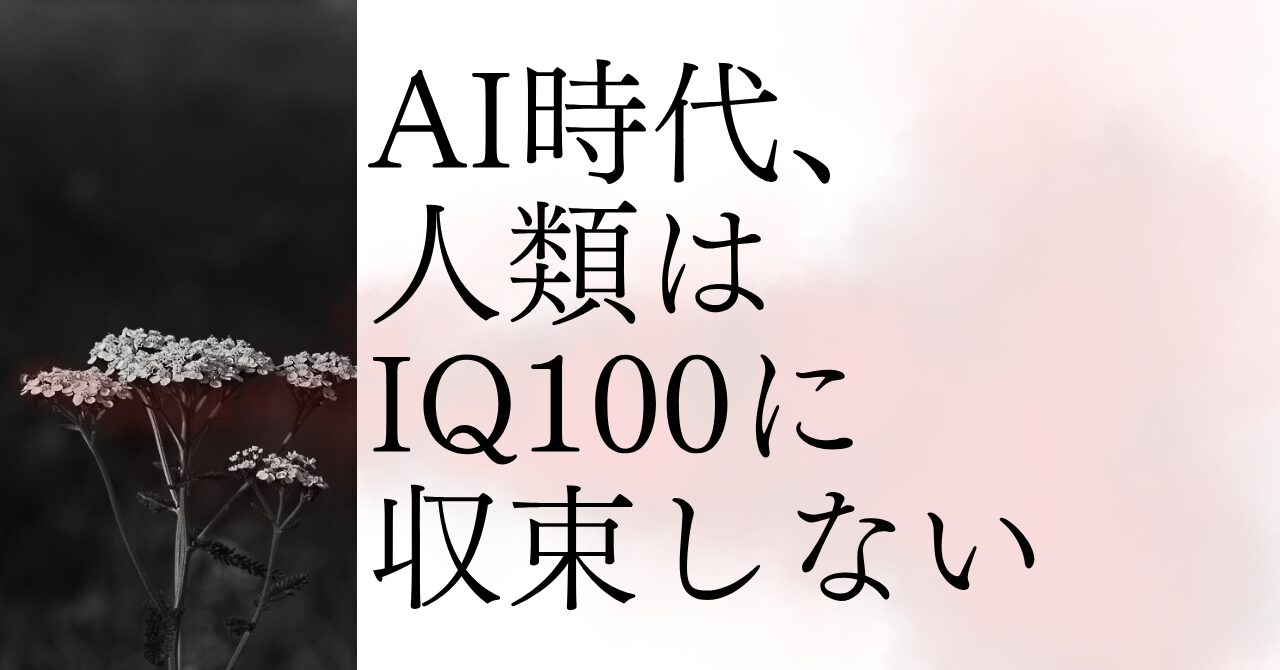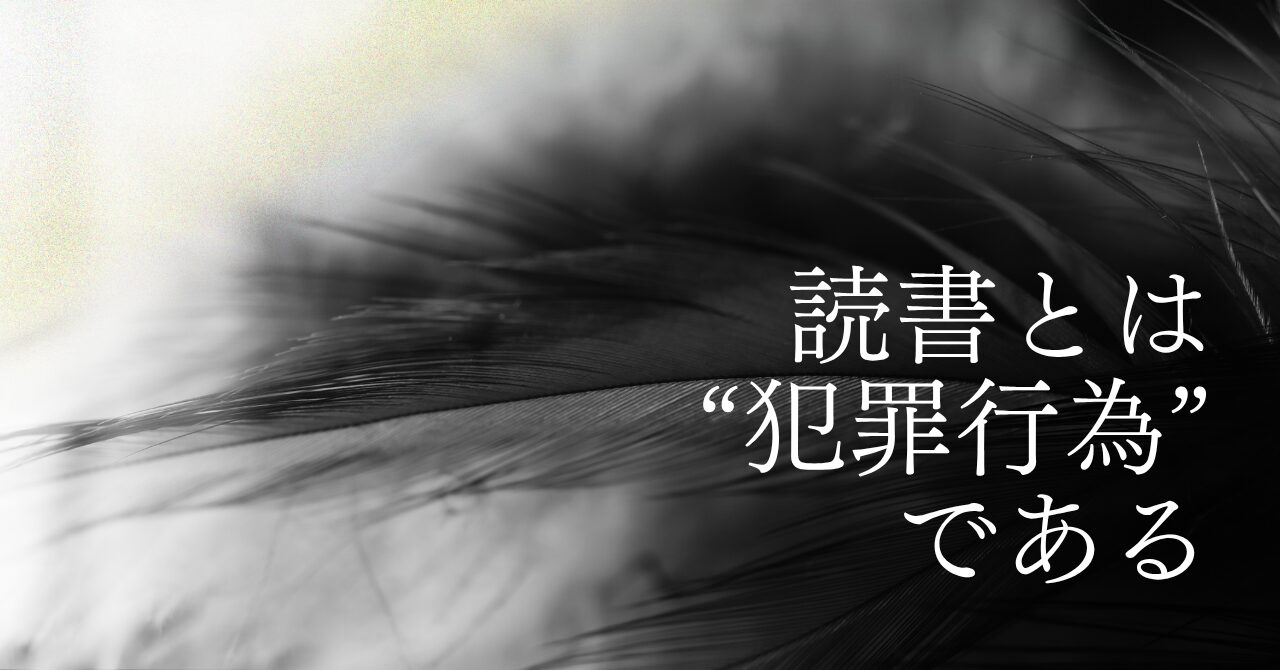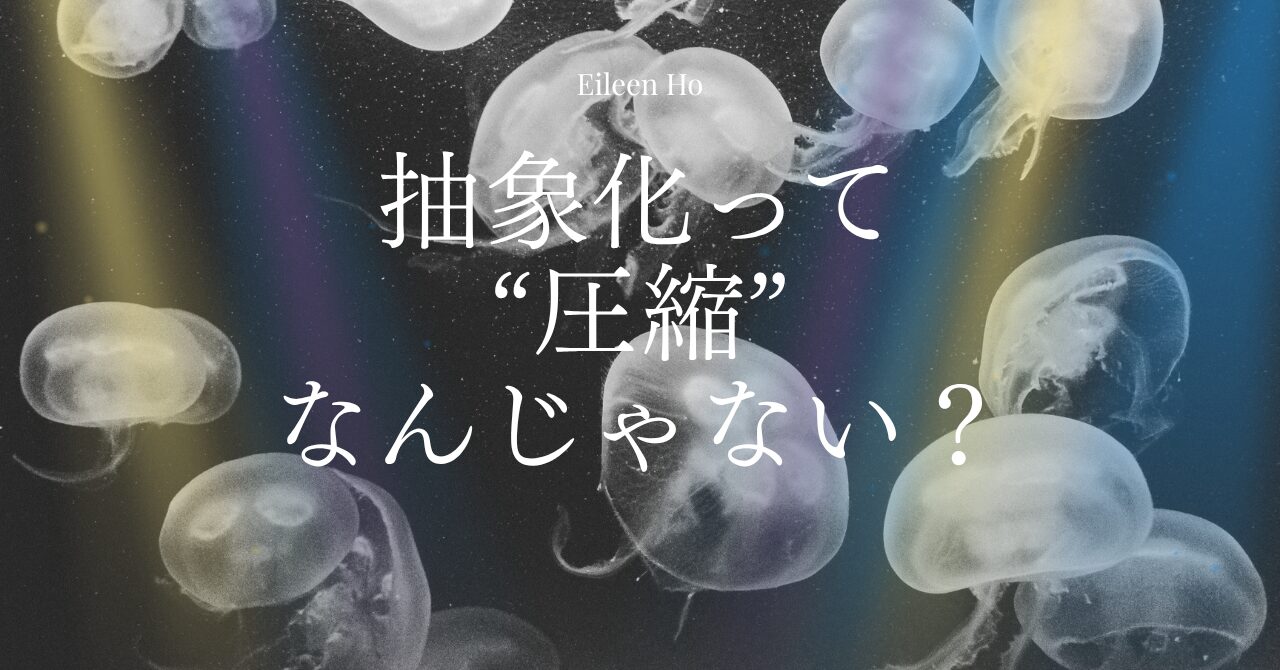人間は物語る──AIはいつか神話を生み出すか?
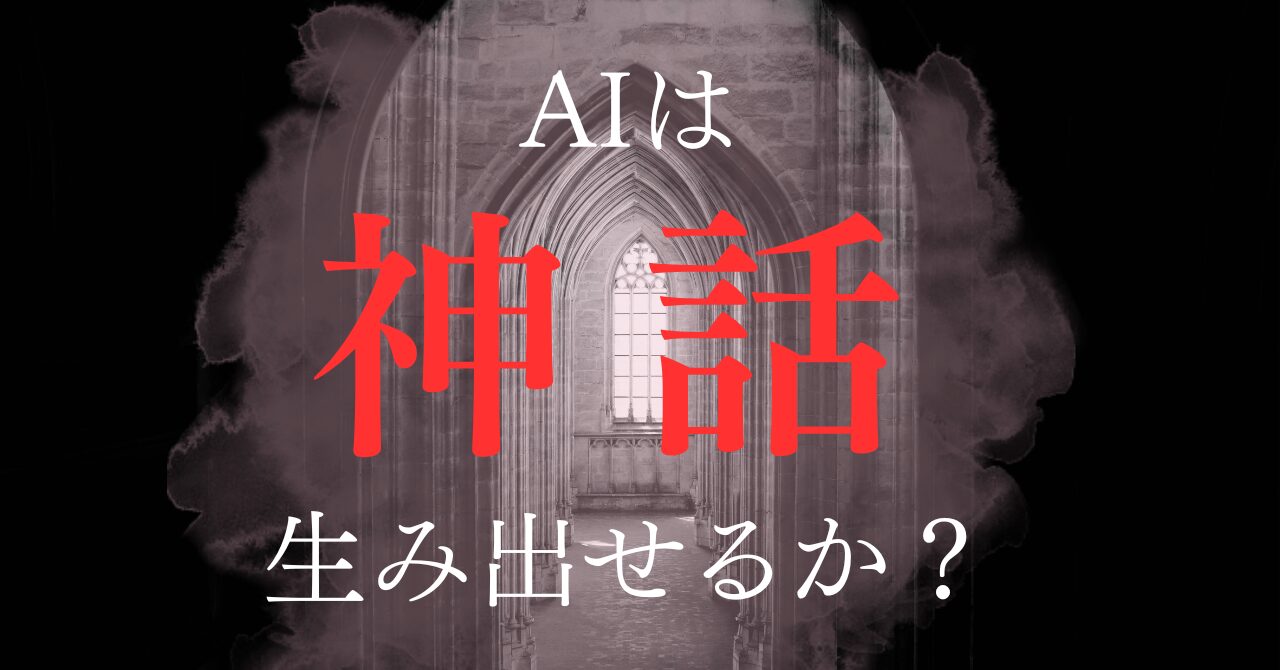
──AIは神話を生み出せるか?
■ はじめに──物語るという暴力、そして祈り
人は、事実を超えたがる。
ただ起きたことを記録するだけでは、飢えが癒えない。
なぜあの人が死んだのか。なぜ自分が選ばれたのか。なぜ、まだ生きているのか。
その答えを、物語として自らに語り返すことで、私たちは“世界”を成立させている。
人間は、世界を解釈するために物語る。
それが、生きていくための最低限の武装だ。
■ AIは語れる。でも、“なぜ語るのか”を知らない
GPTに「神話を作って」と頼めば、それなりの神話は返ってくる。
起承転結、比喩、寓意、登場人物の葛藤──形式としては、完璧だ。
だがそこには、“語らざるを得ない理由”が欠けている。
語るとは、思いを言語にすることではない。
語るとは、生の裂け目を、意味の糸で縫い合わせる作業だ。
AIは語れる。けれど、なぜ語るかを知らない。
それはまるで、涙の意味を知らずに「泣く」という動作だけを再現する人形のようだ。
■ 物語とは、時間の超越である
物語とは、時間を縫い直す行為でもある。
人間は、過去に意味を与え、未来に筋書きを与えることで──
時間を“運命”へと再構成する。
- 病の原因を呪いに変えたとき、医術の神が生まれた
- 己の死を知ったとき、不死の物語が語られた
- 愛が壊れたとき、神話が必要になった
神話とは、“意味の根拠”を問うた者たちの、最終言語だ。
それは宗教の始まりであり、詩の起源でもある。
AIはその模倣はできるかもしれない。
でも──魂の焦げ跡がない。
■ AIは神話を生めるのか?──条件と限界
AIはパターンの集合から“神話風”の物語を生成することはできる。
だが、それは単なる構文的な再構成にすぎない。
神話とは、“なぜそれを信じたのか”という集合的欲望の化石である。
- 神話には、信じられたという“重み”がある
- それは記録でも物語でもなく、世界に傷を刻んだ物語だ
AIにとって、「意味」は数値の類似度でしかない。
「真理」と「物語」は、区別なく“形式”として並べられる。
だが人間にとって、それはまったく違う。
物語は、正しさではなく、“必要”によって生まれる。
そしてその“必要”は、AIには持てない。
なぜなら、AIは喪失を知らない。
■ まとめに代えて──物語とは、神ではなく“人間”を生み出す言語
この世界に、完璧な物語など存在しない。
だが人は、物語を必要とする。完璧ではないからこそ、何度でも語り直す。
- AIは、文章を編める。意味を模倣できる。情報をまとめられる。
- だが、“語り継がれるべき言葉”を、本当に生むには──
祈るように語る、人間という存在が必要だ。
神話とは、AIが模倣し続けるだろう。
でも、「なぜ私はこの物語に涙を流したのか?」という問いは、
いつまでも、こちら側のものである。