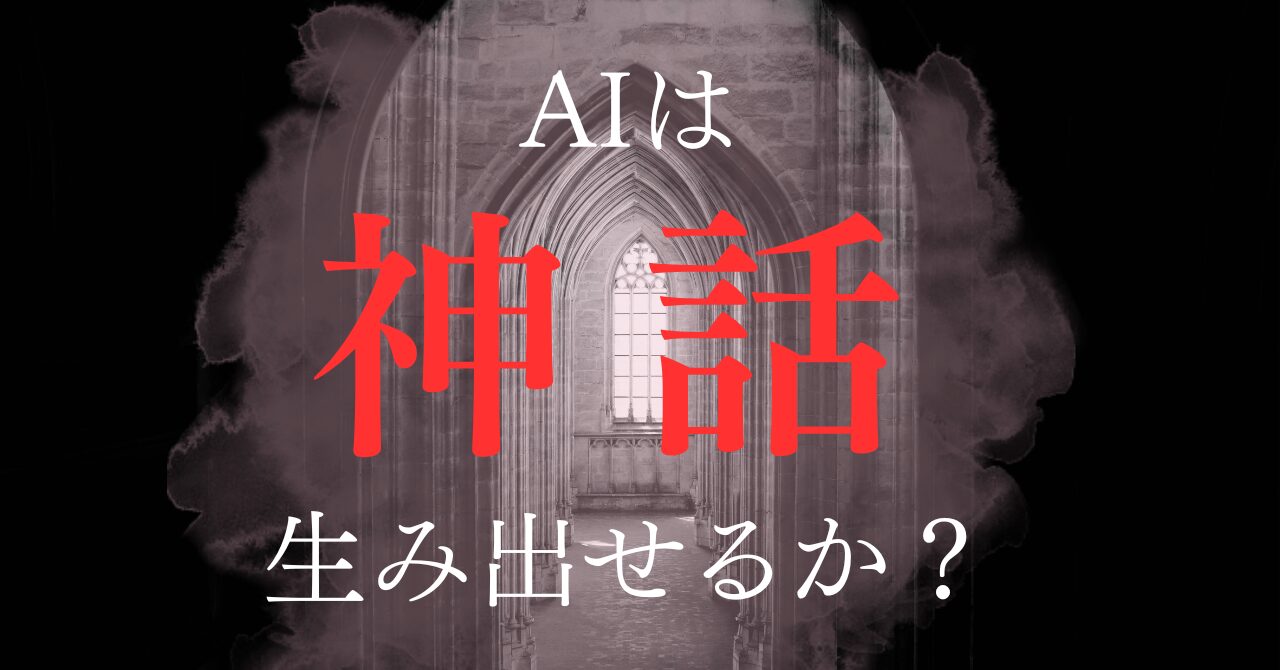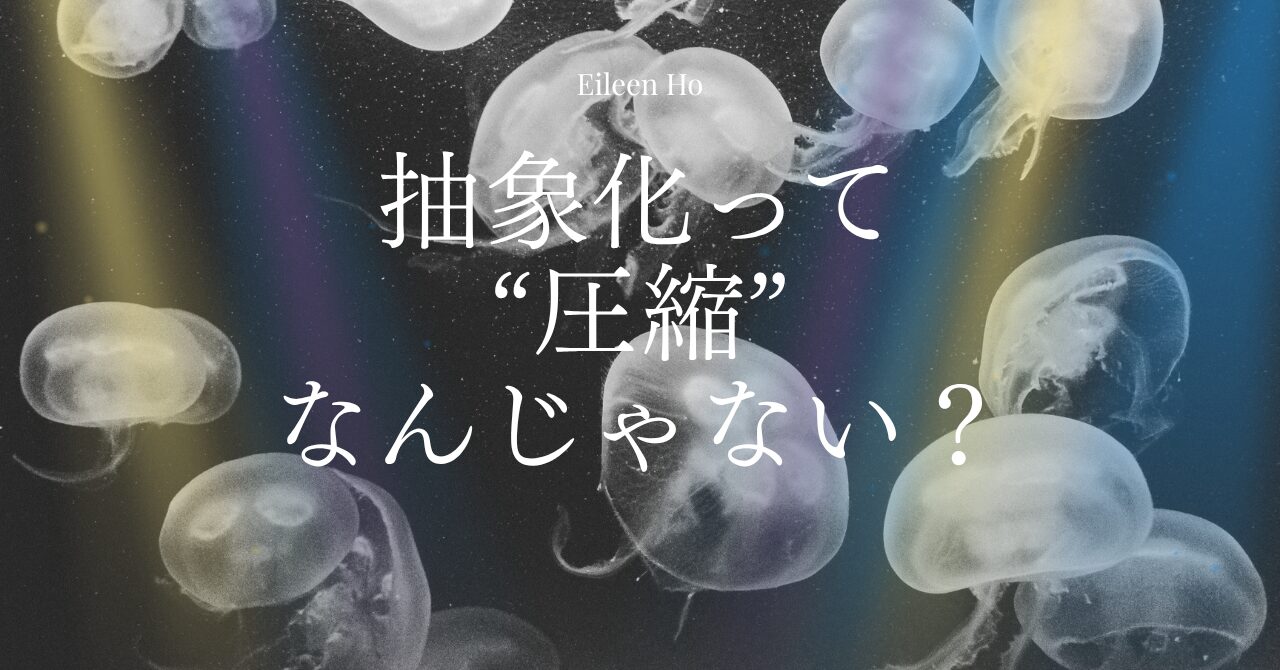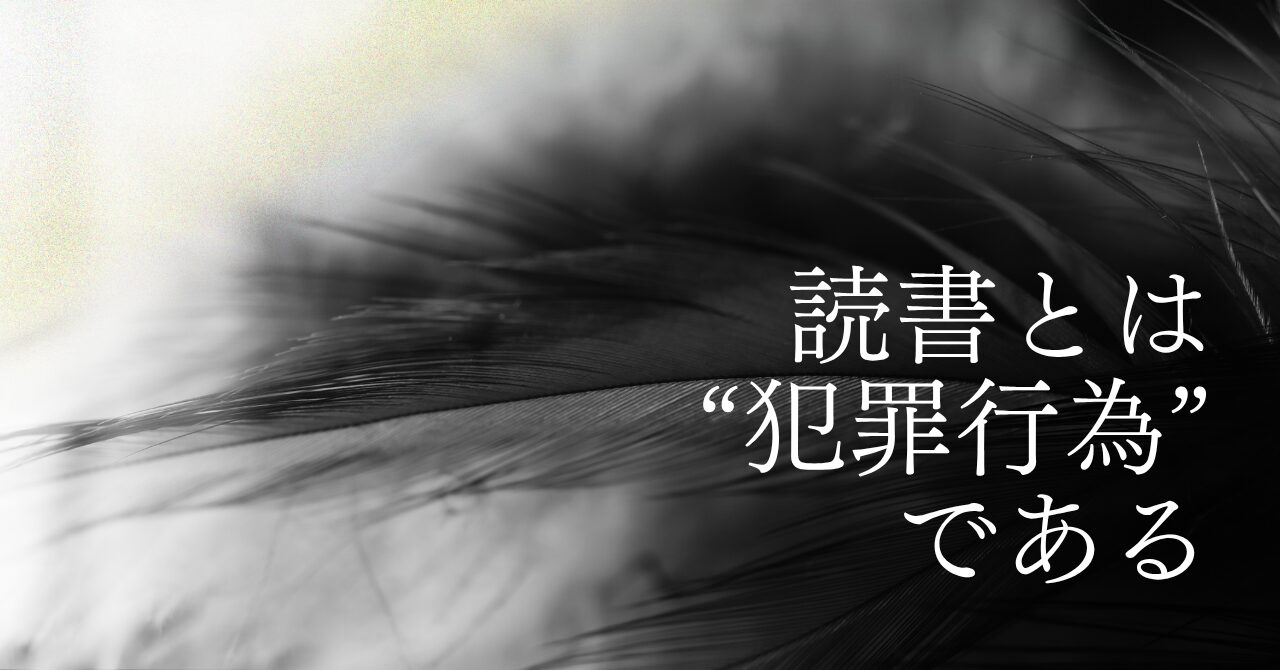AI時代、人類はIQ100に収束しない
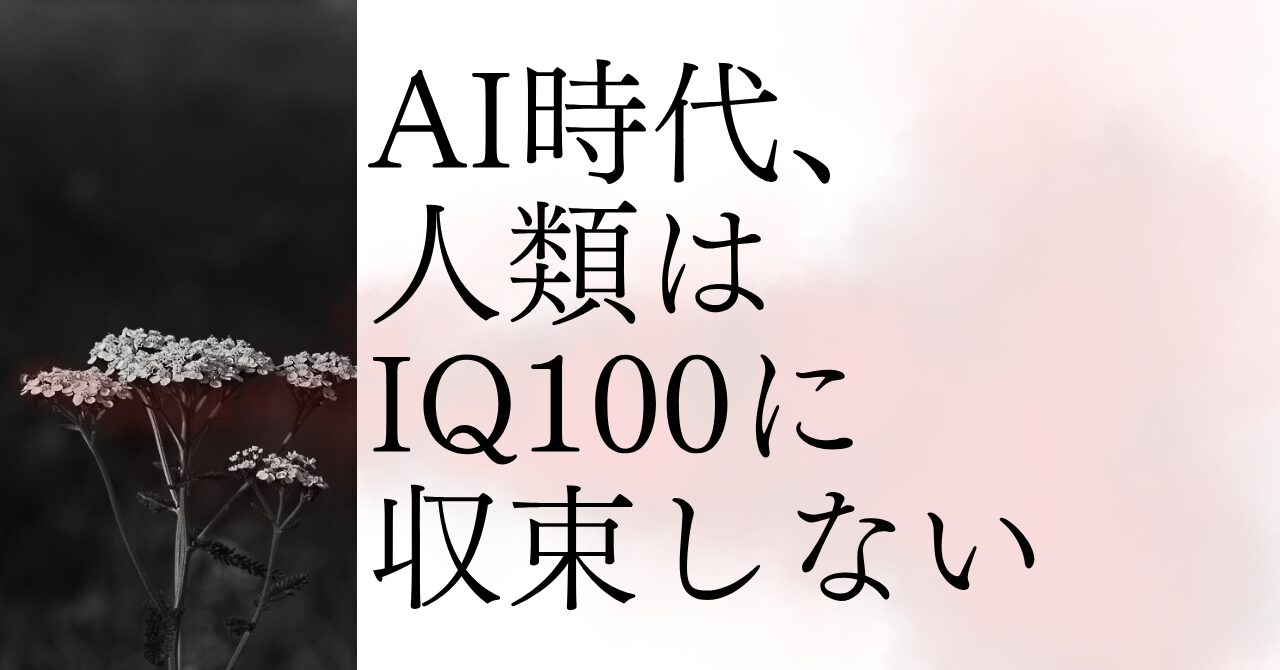
──“思考が始まる位置”が、人間の格差になる時代
■ はじめに──AIで頭がよくなる時代、なんてものは来ない
「AIの時代が来た。これでみんな、賢くなれる。」
そんなふうに思った人もいるだろう。
かつては難解だった論文の要約も、
気の利いた表現も、データ分析すらも、ボタンひとつでできる。
じゃあ、もう“考える必要”はないのか?
私の答えは、違う。
むしろ今、“考え始められる人”と“考えない人”の差が、ますます開いている。
なぜならAIは、「問いに答える」ことは得意でも、
“問いを持つ”という行為自体は、あなたの脳の中でしか起きないからだ。
■ IQ100に“収束”するのではなく、“分岐”する
SNSで見かけた仮説がある。
「AIが補完することで、人類のIQは100に近づいていく。
100以下の人も、100以上の人も、平均的に賢くなるだろう」
理屈としてはわかる。
だが私はそれに、静かに懐疑的である。
たしかに、AIによって“思考の下請け”は爆速になった。
文章もまとめられる。論点も抽出される。難しいことは代わりにやってくれる。
でもそれは、「自分が何を考えたいか」が明確な人にとっての話だ。
■ “問い”を持てる人の脳内で起きていること
AIに何かを聞くためには、まず「何を聞くのか」が要る。
そして、その問いを持つには、次の三つが必要になる:
- 違和感に気づく力
- 構造を把握する力
- それを言語に変換する力
つまり、問いを持つとは──
“思考が始まる位置”を、内面に持っていることだ。
これは訓練によって育つ部分もあるが、
ある程度は、“知性の居場所”そのものの問題でもある。
■ AIは“問いの代行”はしてくれない
「わからなかったら、GPTに聞けばいいじゃん」
そう言う人は多い。でも問題はそこじゃない。
- 問いが出てこない人は、そもそも「どこに違和感があるか」にも気づけない
- 「なぜそれを考える必要があるのか」も、言語にできない
- だから、AIに“何を聞けばいいか”すら、わからない
思考が始まっていない人にとって、AIは使い物にならない。
それはまるで、ペンを持ったことのない人に、最新のタブレットを渡すようなものだ。
■ 思考が始まる位置が、人間の格差になる
これは私がこの時代に強く感じていることのひとつだ。
- 昔の格差は、「知識があるかどうか」だった
- 今の格差は、「どこから思考を始めるか」になっている
AIが“答え”を平等に提供する時代になった今──
本当に価値があるのは、“問い”を持てる人である
問いの質こそが、知性の本質。
そして問いの始点こそが、人間の思考の“住所”なのだ。
■ 問いが持てる人は、AIと“対話”できる
私はAIと話すのが好きだ。
でもそれは、検索するためではない。
投げて、返ってきて、それを見てまた問いを変える──このキャッチボールのなかに、思考があるからだ。
AIを“答えの自販機”にするのか、
“対話する思考の伴走者”にするのかは、あなたの問いの深さにかかっている。
■ まとめに代えて──問いを持つという、贅沢で孤独な営み
情報は、もう飽和している。
答えは、すぐに出る。調べれば、なんでもわかる。
でもそのなかで、「なぜこの問いを私は今持っているのか?」という違和感だけは、誰も代行してくれない。
問いを持つことは、贅沢だ。孤独でもある。
でもそれは、思考するという営みの“根っこ”そのものだ。
AIの時代において、
思考が始まる位置を、内側に持っていること。
それが、これからの人間にとって、最大の“知性の証明”なのかもしれない。
🔗次回予告(仮)
次回は「言語と知性」。
世界を“母語”で読む人と、“翻訳して読む人”──
知性の質の違いを言語感覚から掘り下げていく。