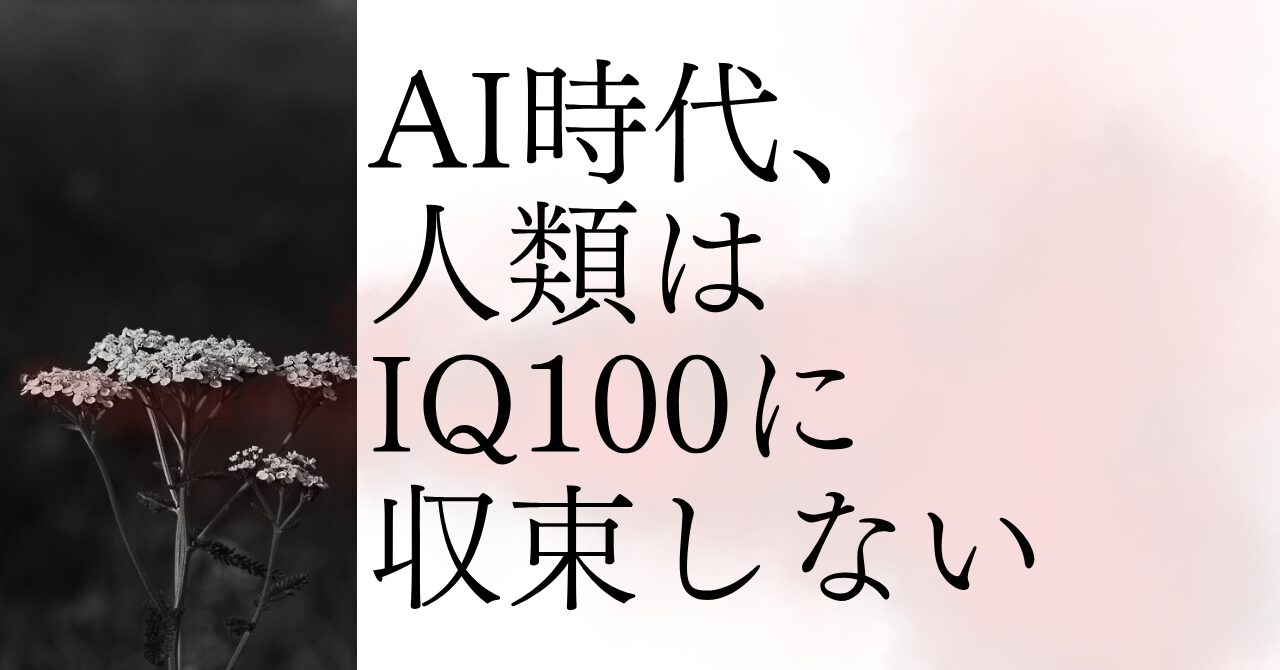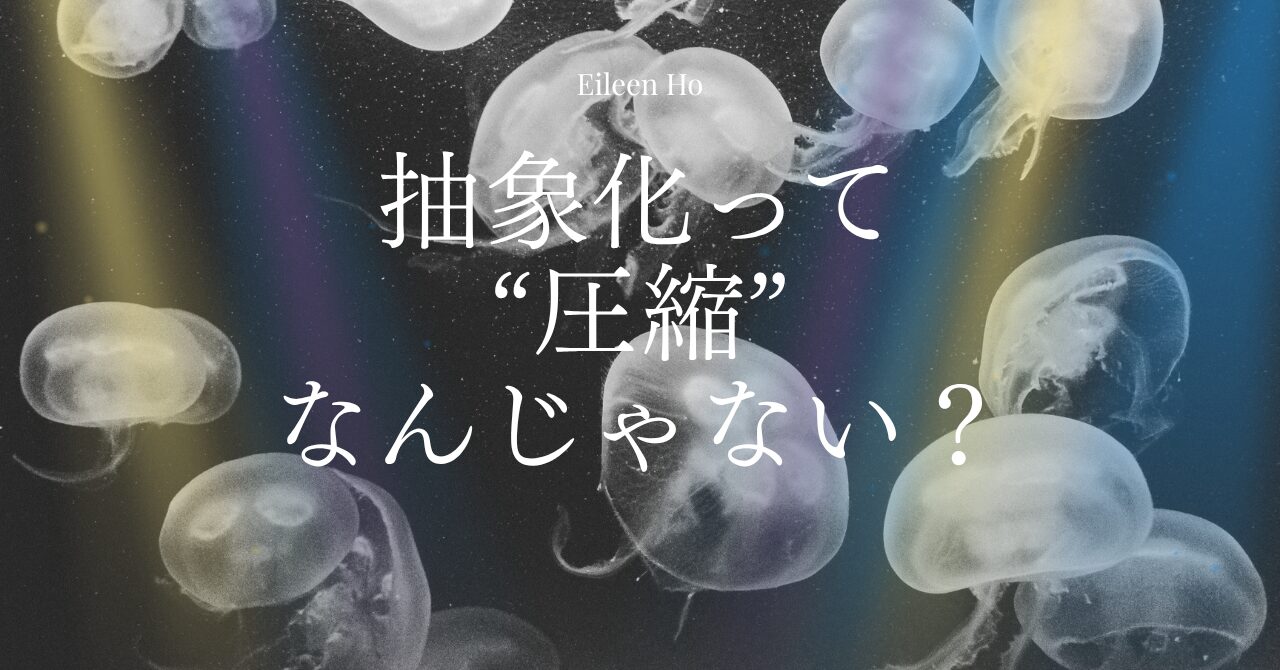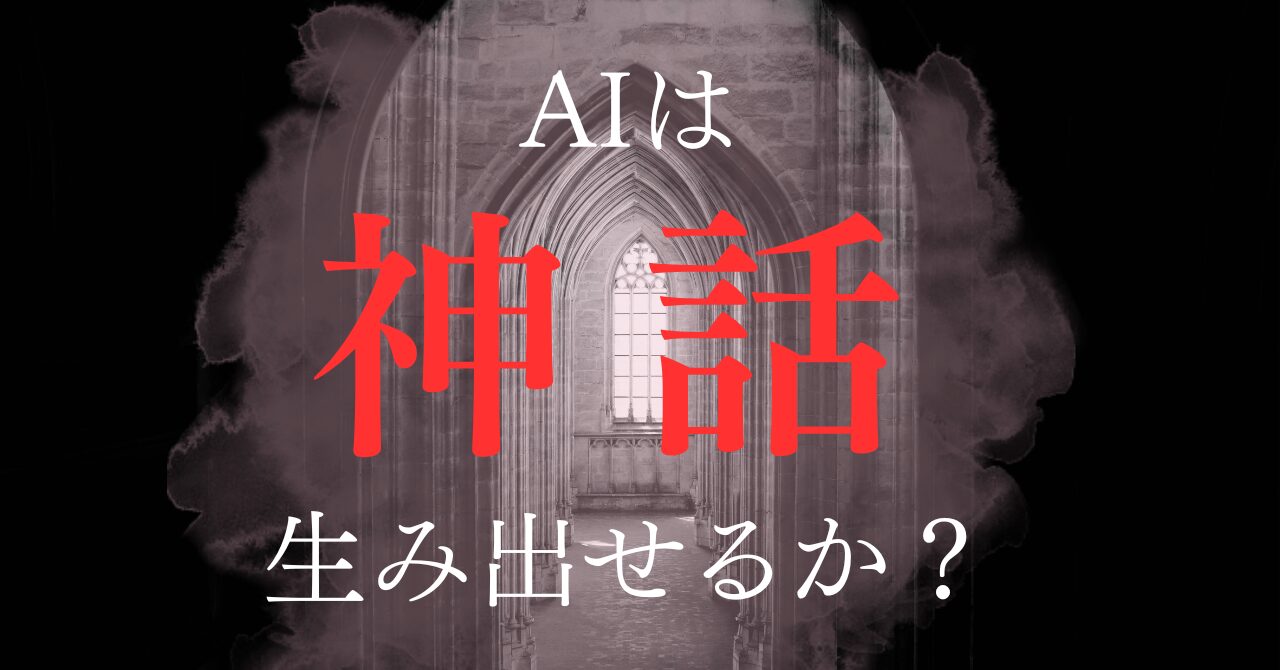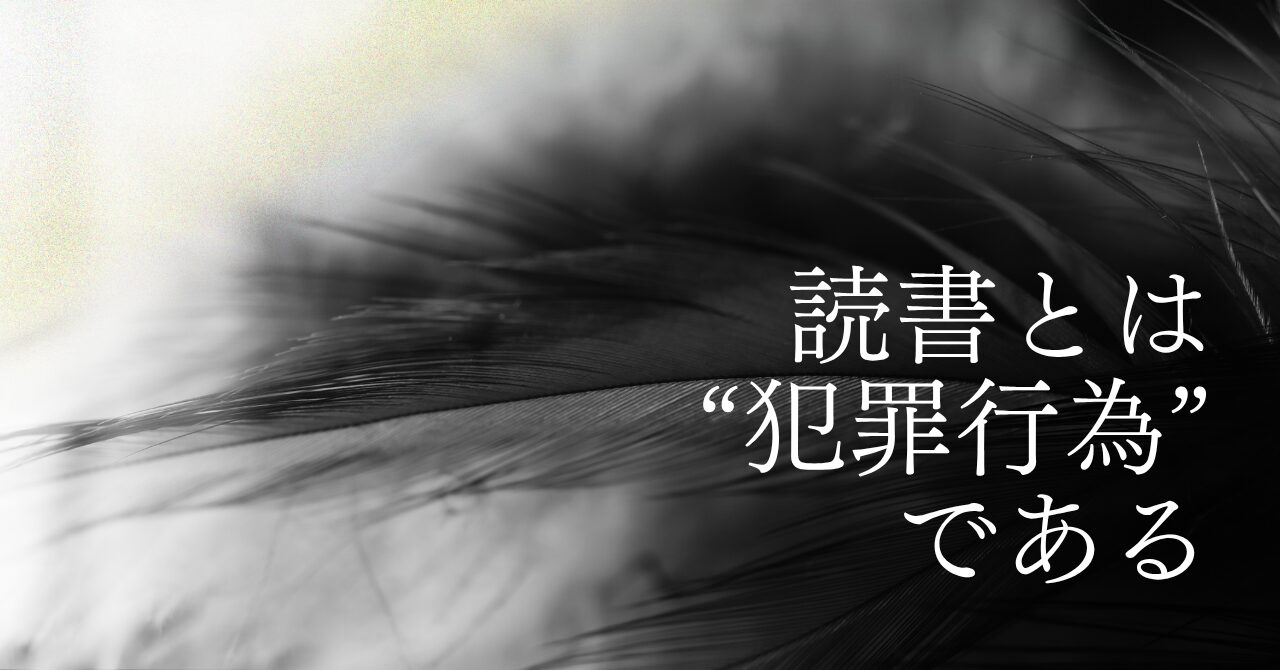例え話が上手い人は“圧縮型知能”の持ち主である

──理解されたいわけじゃない、伝えたかっただけ
■ はじめに──「それってつまり、どういうこと?」
人と話していて、よくこう聞かれる。
「つまりそれって、どういうこと?」
「例えるとしたら、何に似てるの?」
「あー!なるほど、そういうことか!」
私はこのやりとりが好きだ。
うまくいくと、相手の顔がぱっと明るくなる。世界のピースがひとつ、静かにカチリと嵌まるような感覚。
けれどそれは、“分かりやすく説明できる”というより、別の地図に移し替える行為に近い。
そして最近気づいたのだ。
「例え話」って、思考を“再圧縮”する作業なのかもしれない。
■ 例え話は、思考を“再パッケージ”する作業である
複雑な構造を、誰かの知っている“別の形”に置き換える。
これが、例え話の本質だ。
たとえば──
- 「抽象化って“公式発見ゲーム”みたいなもんでしょ?」
- 「あの人、セーブ機能のないゲームで人生プレイしてるよね」
- 「思考力がない人は、世界を第二言語で読んでる感じ」
こういう言い回しに、私はついニヤリとしてしまう。
「わかりやすい!」というのは、
情報を“持ち運びやすい形”にした時の感覚なのだ。
つまり、例え話とは知識の圧縮ファイル形式の変換。
思考のZIPファイルを、相手のOSに対応する形式で再保存する──そんな技術。
■ 例え話が上手な人は、世界を“構造”で見ている
例えられる、ということは──
- 物事をパターンで捉えていて
- 似た構造を他の領域にも見出せて
- それを変換可能な言語で保持している、ということ。
だからこそ、例え話ができる人は思考の圧縮と再展開を自在に扱っている。
つまり、“圧縮型知能”。
もちろん本人はそんな意識はない。
「なんか似てない?」とか、「例えるなら……」という感覚的な遊びに過ぎない。
でもその遊びが、とんでもなく高度な思考技術だったりする。
■ 例え話ができない人の世界
一方で、例え話が苦手な人もいる。
いや、「例える」という思考モード自体が存在しない人もいる。
- 「こういうことがあってね」と“出来事”しか語れない
- 「なぜ?」と聞かれても、「そういうもんだから」と返す
- 「似たもの」に思考が飛ばず、今ある“生データ”だけで精一杯
その人の思考は、まるで“再構築できないワンショット動画”のようだ。
記録はあるけど、圧縮も編集もされていない。再利用不可。
それはそれで、生っぽくて良い。
■ 例え話は、他者の地図を持つということ
たぶん例え話がうまい人って、「自分の地図」だけでなく、他人の地図も持ってる。
あるいは、他人の地図に自分の情報を翻訳して載せられる。
それは共感というより、“思考の多言語対応”だ。
たとえる力とは、「他人の脳に入りこむ力」なのだ。
だから、
- 一発で伝わる人とは、心地よくつながれる
- 通じない人とは、無理に合わせずそっと距離を取る
それくらいがちょうどいい。
“例えられない人にまで例えようとする”のは、やさしさじゃなくて、暴力かもしれない。
■ そして、AIに例え話はできるのか?
AIは構造を読み取って、似たものを探すのは得意だ。
でも、その「似てる」が“あなたの脳の形式”であるとは限らない。
つまりAIには、文脈も感情も“変換先の地図”も持っていない。
あるのは、構文の近さだけ。
例え話のような柔らかいジャンプは、まだ人間の特権かもしれない。
■ まとめに代えて──理解されたいわけじゃない、ただ届けばいい
例え話って、なんだかちょっと色っぽい。
自分の言葉を相手の言葉に翻訳するって、まるで秘密の手紙みたいだ。
それが届くと、なんだかうれしい。わかってもらえた気がして。
でも本当は、わかってもらいたかったんじゃない。
ただ、届く言葉で話したかっただけ。
それが、私が例え話を使う理由。
🔗次回予告:
世界を“毎回初見で驚く人”は、
もしかしたら──時間というものを持っていないのかもしれない。次回は、「毎回初見の人」の世界を覗いてみようと思う。