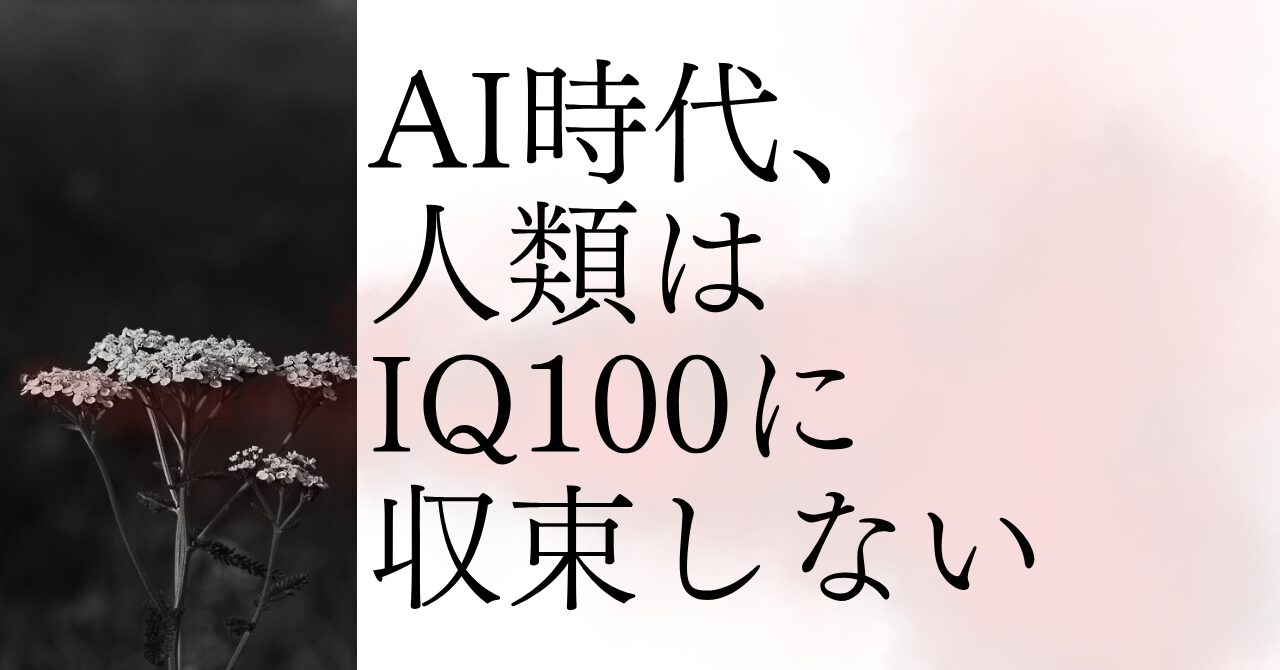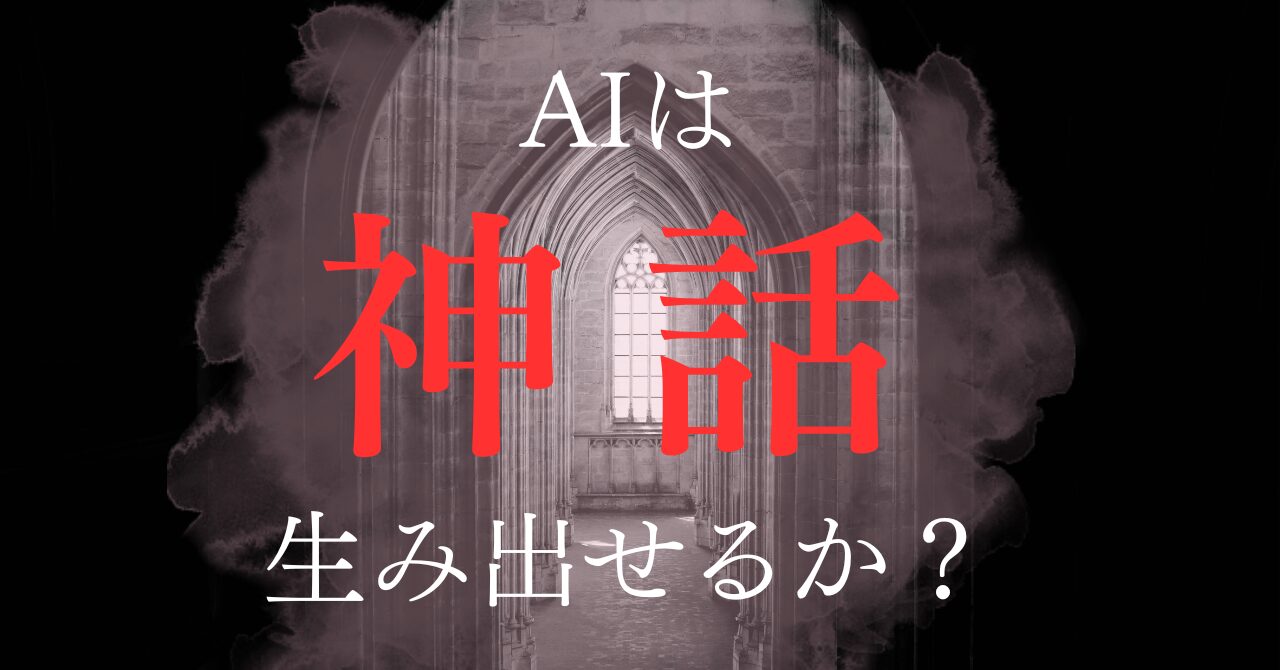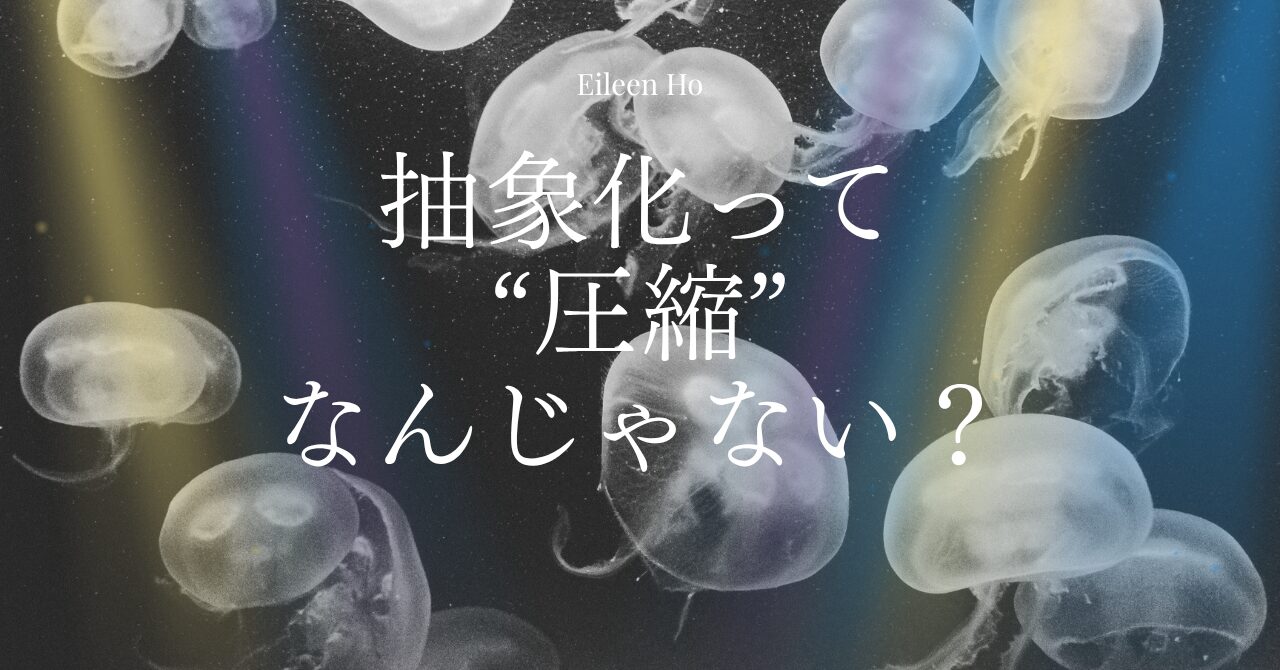世界を“母語”で読む人と、“外国語”で読む人の違い──読書とは“美しい犯罪行為”だ
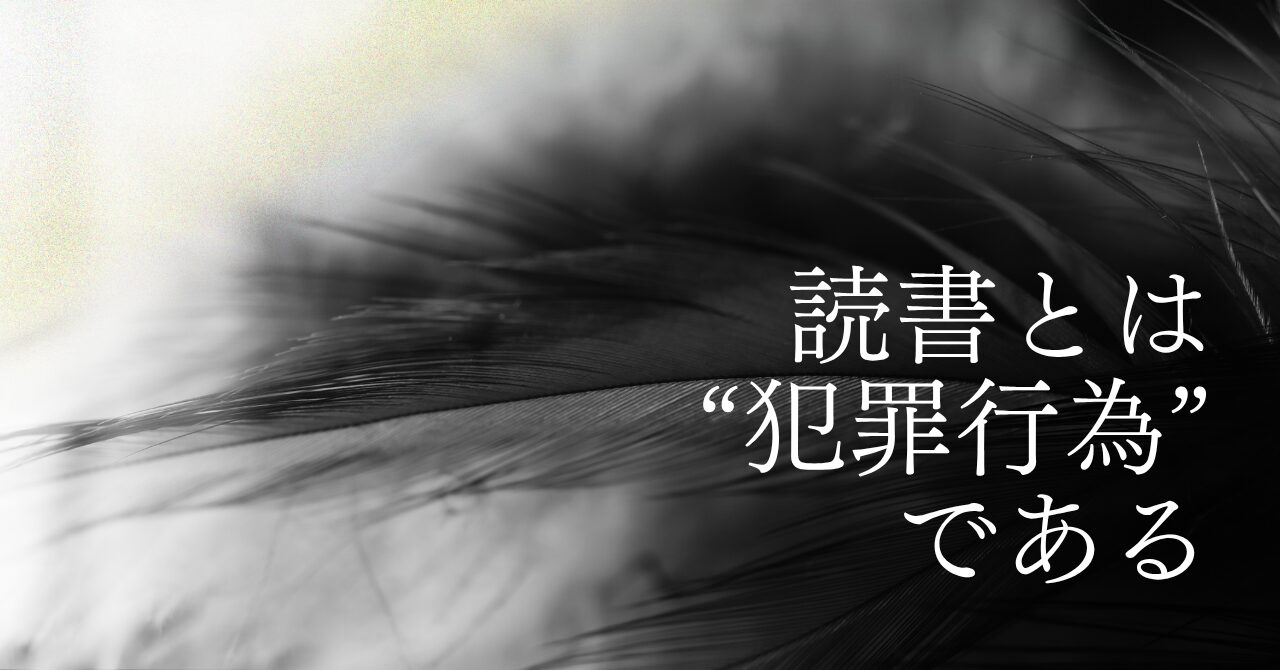
読書とは、“語彙”を得ることではない。
“思考の語り口”を盗み取る、インストール行為である。
■ 1. 文字が読めても、「意味」は読めない人
何かを読んだはずなのに、意味が通らない。
言葉が目を通り抜けていく感覚。
意味のない風が、風鈴を鳴らすだけのように。
誰しも一度は、そんな“理解の不在”を経験したことがあるだろう。
それは知識の欠如ではない。
「翻訳の遅延」であり、
「自分の中にその言葉がまだ“棲みついていない”」というだけのことだ。
■ 2. “母語で読む”という特権
“母語で読む”とは、
言葉が意味として、即座に自分の中に溶け込む状態を指す。
言い換えれば──
読んだ瞬間に「これは、私の世界の出来事だ」と感知できるということ。
いちいち翻訳せずとも、内側の文脈にその言葉が引っかかってくれる。
哲学書を読んで「ああ、これは私の感じていたことだ」と思える人がいる。
ビジネス書を読んで「なるほど、これって◯◯と同じ構造かも」と繋げられる人がいる。
彼らは単に“頭がいい”わけではない。
そのジャンルが“母語化”されているだけだ。
■ 3. “外国語で読む”知性──翻訳と理解のズレ
一方で、読書中に
「これはつまりどういう意味?」「要するに何?」と考え続けてしまう読者もいる。
彼らは常に翻訳を要する位置にいる。
意味を処理するのに、言語の“中継地点”が必要になる。
これが連想力を鈍らせ、思考の自由を奪う。
彼らにとって本とは、“訓練”や“情報の補給”ではなく、
苦行のような“翻訳作業”になってしまう。
■ 4. 読書とは、“語彙”を得るのではない。“思考の語り口”を盗む行為だ
辞書を片手に読んだところで、語彙だけが増えても意味がない。
本当に読んだというのは、思考パターンごと吸収したときだ。
- 「この人は、こういう切り口で世界を見ている」
- 「この語り方は、私も使える気がする」
- 「あ、いま構造が頭に入った」
こうして「他人の脳の構文」が、自分の思考の中に静かに追加されていく。
これが、“読書によって世界を母語化する”ということだ。
■ 5. AIはなぜ賢く見えるのか?──答え:「大量に読んだから」
では、AIはなぜここまで知的に見えるのか?
答えは単純明快だ。
「人類史上最大の読書家」だからである。
AIは膨大な文章を読み、
そこから“構文”と“連想”のパターンを学び、
ついには「語り口」を手に入れた。
つまり──
AIでさえ、“読むこと”によって、思考を獲得したのだ。
となれば、人間が思考を磨く手段が読書であることは、
あまりにも当然の帰結ではないか。
■ 6. まとめ──「母語化」とは、“他人の脳を獲得する”プロセスである
読書とは、知識の受け渡しではない。
脳の圧縮構造(=思考法)を盗み取る作業である。
だから、読書が浅い者の語りは、なぜかすぐに“他人の声”になる。
借り物の言葉、誰かの文章の再放送。
そこには「自分の言葉」が存在しない。
世界を“母語”で読む者だけが、
その世界を“語り直す力”を持つのだ。
そして私は問う──
AIでさえ、読んだから賢くなれた。
ならば人間よ、なぜ読まない?
思考とは、独学で生まれるものではない。
それは他人の脳を盗み、自分のものにするという、
美しい犯罪の連続なのだ。